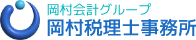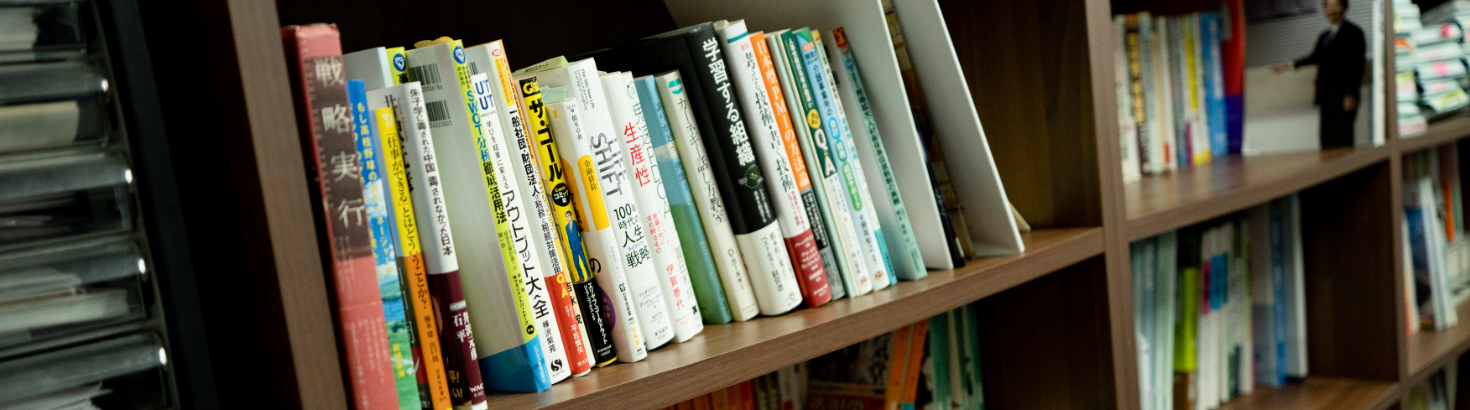令和6年1月1日以降の相続等から区分所有マンションについての評価通達の改正が行われた。
令和4年4月19日の最高裁「評価通達6項事件」を受けてのものである。同事件の内容については、WEB等でご確認いただければと思うが、最近のニュースを見ていても相変わらず都市部の新築マンションの高騰ぶりが報道されている。
このことは、相続とマンション購入にさほどの相関関係が無いという事実を表したものかと思うが、ここであらためてマンション評価の何が変わったのかということをおさらいしておく。
元来の評価方法は、以下の式のとおりである。
相続税評価額 = 建物の固定資産税評価額 × 倍率(1.0)× 敷地権割合
それが令和6年1月1日以降は
相続税評価額 = 建物の固定資産税評価額 × 倍率(1.0)× 敷地権割合 × 区分所有補正率
上記の通り、“区分所有補正率”たる乗数が一つ加わることとなった。
この区分所有補正率の計算は国税庁のHPで計算表のエクセルシートをダウンロードしたら簡単に計算できるもの。ただ、ここでは考え方について触れておきたい。
区分所有補正率の計算要素になるものは以下の通りである。
① 築年数 ⇒ 新しいほど評価が高くなる。
② 総階数 ⇒ 高いほど評価が高くなる。
③ 所在階 ⇒ 高層階であるほど高くなる。
④ 敷地持分狭小度 ⇒ 小さいほど高くなる。
最後に①+②+③+④の指標に3.22を足した数が「評価乖離率」とされ、それを1で割って「評価水準」を算出し、その評価水準によって「区分所有補正率」が変わってくる。これは全てエクセルで自動計算されるので覚える必要はない。ただ、この評価水準の考え方は参考になるので、少し詳細を記しておく。
“評価水準”とは
まず、評価水準とは何なのかということであるが、評価乖離率が高い、すなわち実勢とかけ離れている場合には評価水準は下がる。
一方評価乖離率が低いと実勢価格と乖離していないということで、評価水準は上がる。
評価水準と区分所有補正率の関係
評価水準をベースに最終乗数たる区分所有補正率が決定する。その関係は以下の表のとおりである。
区分
区分所有補正率
①
評価水準<0.6
評価乖離率×0.6
②
0.6≦評価水準≦1
補正無し
③
1<評価水準
評価乖離率
まとめ:タワマン節税は未だ効果あり
いわゆるタワマンは①に該当するケースが多い。すなわち評価乖離率に60%を乗じた数をもって補正率とする。
ここは注目すべき点で、補正率で評価額と実勢価格の差を埋めながらも、40%は評価を下げてくれているのである。なので、やはり相続対策に不動産投資は一定の効果を保持し続けると結論付けていいのではないか。
②と③に該当するのは、築年数が古く比較的低層階の区分所有物件である。中でも戸数が少なく、敷地権割合が大きくなりがちな物件が③に該当すると考えていい。
試してみたが、③に該当させるのは結構難しい。なので、多くは①か②であろう。
相続対策を考えての資産運用はあらかじめ税理士等の専門家に相談するのが上策である。ちなみに税務署へ行っても税理士に相談するよう促されることが多いように思う。